こんにちは、てぃさんです。
今回は、SESを活用したキャリアアップの活かし方という内容を記事にしたいと思います。
世間一般的にはSESの会社はブラック企業やら社員を使い捨てにしてエンジニアとしてキャリアアップできない、というイメージが強いのではないでしょうか?
確かに、SESでもそういったネガティブな会社もあると思いますが、私の肌感覚で言うとそういう会社の方が少ない、むしろ一緒に仕事したことない、もしくは、働いている方の捉え方次第だと感じているのです。
てぃさん自身も現在はSESでお客様のシステム開発に従事しています。
SESのネガティブなイメージにあえて抗おうとしているのは、私自身、SESというサービス自体は素晴らしいと考えているのと、SESだからこそできるエンジニアのキャリアパスがあると考えているからです。
これからITエンジニアを目指す方、駆け出しのITエンジニアの方のキャリアアップの参考になればと思います。
(SESとは?や契約形態などについては、過去の記事 や他のサイトさんで詳しく説明してくれているので、この記事では割愛させていただきます)
SESの会社に入るメリット
希望の言語、技術に携わりやすくなる
SESとして得られるメリットはこの部分にあります。これは断言して言えることです。
IT技術の流行り廃りは早く、必要な技術の需要も年単位で変わっていくものです。
2016年, 2017年あたりからPythonが機械学習やディープラーニングというワードと共に、一気に需要や収入の高い言語の一つとなったことは記憶に新しいですね。
TIOBEのランキング
2016年 ランキング:5位 シェア率:3.8%
2020年 ランキング:3位 シェア率:11.7%
2022年 ランキング:1位 シェア率:16.3%
となってます。
今やJavaやCより注目されている言語であるこがわかります。
このようにシステム開発に求められる技術の移り変わりは早く、エンジニアとしてもそれら技術のキャッチアップを行い、自身の武器として実際にどれを習得すべきかを見極めて、身につけていく能力が必要です。
SESの一つの動き方として案件・プロジェクト単位で動きやすいので、自身のスキル計画に合わせて関わる仕事を変えやすいというところです。
企業側もレガシーなシステム保守・運用業務においては新しい技術を採用するリスクの方が高くなってしまうため、新しい技術を採用することはありません。
開発業務に集中しやすい
一般的にはエンジニアは好きなプログラミングだけをするこのではと思っている方も多いと思いますが、自社サービス会社やSIerにおいては組織の社員(「プロパー」といいます)としてやることも求められます。
それこそ、SESなどの要員調整やプロジェクト全体で起こる問題の解決(これはかかわる役割にもよりますが)や報告などなど。
具体的な例を挙げるとすると、面倒を全体的にみる企業、チームでかつECを扱う場合は、障害監視や対応を責任もって対応することが求められるため、プロパーさんは土日深夜対応を行ったりします。SESは契約にもよるが基本的にはプロパーさんが優先対応することが多い。
エンジニアでカバーする領域が広いため、責任をもって仕事できるという反面、プログラミングだけやることをイメージと異なるでしょう。
SESにおいては基本的には参画時にやってもらいたいことが取り決められるため、プログラミングであればプログラミングをメインに行うことが多いです。(スキルが上がってきたら設計や要件定義なども行います)
そういう意味で、開発業務に集中しやすいと言えます。
労働時間が調整しやすい
SESはエンジニアが行う業務の時間によって企業間の支払いが変わる業態となり、大体、月間140時間から180時間のあいだで業務することを求められるのです。
そのため、180時間を超える場合はその分の費用が掛かってしまうため、クライアント側は長時間労働にならないように業務量を調整してくれるのです。
リリース前などの繁忙期は忙しくなったりしますが、1日の予定が立てやすいため、IT業界の中では勉強の時間や自分の時間を確保しやすいと思います。
大規模な案件に携われる
SESの特徴で上げた案件・プロジェクト単位で参画することができるため、発注側の優良企業側が行うシステム開発プロジェクトに参画することができたりします。
大規模案件ではグローバルな優良企業が行う案件ということもあり、相場よりも単価も高い傾向があります。
キャリアとしても有名企業の案件に従事したという実績を詰めることで、今後ほかの案件に参画するときのスキルアップやアピールポイントにできるというメリットもあります。
会社員+フリーランスのメリット感
SESの企業によっては自身の単価の80%を社員に還元する(月間単価100万であれば80万)企業もあります。
フリーランスにないSESに所属する会社員としては、福利厚生を受けれたり(IT健保だとうれしい)、その人に会った案件を探してくれるため、何も仕事がないというリスクがないのではと思います。
スキルアップすれば単価も上がり、その分社員に還元してくれる会社であれば自身の給与もアップする。ということになります。
逆のフリーランスのメリットももちろんありますが、スキルが低い人で将来フリーランスを目指す人にとって、SESはよいステップになると思います。
プロフェッショナルとして力を発揮するのSES
IT業界だと何故か下に見られるSES。。。
大手SIerから階層構造的に下流の会社に仕事が流れてくるということから、SESをよく知らない人たちからもやばい存在になってしまったのかなと思います。
確かに、業界構造的にSESの会社選びは重要です。駒の様に扱う会社やスキルが上がっているのに給料が上がらないなど。しかしながら、SESでも優良企業は存在しています。
てぃさんが仕事の本質として考えるのは、「課題を解決して対価を得る」ということです。
SESはシステムのエンジニアリングに対してのサービスを提供し、困っているお客様の問題を解決するエキスパートと考えています。
システムのリプレースをしたいがどう進めていいかわからない、新しい技術で効率的に開発を行いたいが、自社のエンジニアだけではスキルも人員も不足しているため、外部のエンジニアにサポートを受けたい。
システム開発における問題課題を解決の一翼を担っていると。
それには、技術のキャッチアップや自己学習でスキル向上するための鍛錬が欠かせません。
ただ、できるエンジニアは自己研鑽を息をするように楽しんでいるように感じます。
日々刀を研ぎながら、課題の問題にいつでも切りつけられる準備をすることがプロフェッショナルである条件であり、SESだからテスターしかできないのは、刀の研ぎ方を知らない、していない方がの言い訳でしょう。(でそういう人たちに限って「ブラック」と流布していると思ってしまうんですよね)
SESを活かしたキャリアアップの方向性
SESにおすすめな方の例を挙げたいと思います。
駆け出しエンジニア
プログラミングスクール卒業生や独学でエンジニアを目指して勉強している方。
まずは、業務実績を積むためにSESを利用しましょう。
履歴書上勉強はアピールになりません。自分独自の作品(ポートフォリオ)があれば別ですが、駆け出しエンジニアで一つの作品を作り上げるのも時間がかかってしまうでしょう。
その時に、自身のやりたいことに近しいことができるSESであれば、案件、言語などを考慮して実務経験として実績を積むことが可能となります。
スキルチェンジしたいエンジニア:
Webアプリケーションから例えば、VRやゲーム関連のスキル、エンジニアを目指したい方。
一般的に募集枠は多くないですが、未経験でVRやゲーム関連の会社に就職は狭き門なのではないでしょうか。
SESの中には、VRやゲーム関連の募集案件もあり、SES経由でそういった案件に入り込むことも可能だったりします。
VRやゲーム関連は一つの例ですが、ブロックチェーンや他のIT業界へのスキルを身に着ける術としてSESを活用することも可能でしょう。
プロフェッショナルを目指すエンジニア:
フリーランスと変わらないかもしれないですが、技術を極めて難しいプロジェクトを渡り歩くことを目指すエンジニアにとって、SESを活用することも一つの手だと思います。
ユーザ企業だと一つのプロジェクトが終わるとしばらく落ち着いてしまうということもありますが、次々と難しいプロジェクトをこなして市場価値を高めるためにもSESを活用できると思います。
その場合は、それに見合った給与がもらえるか、給与アップの条件などを確認することを忘れずにしましょう。
以上、「SESを活用したキャリアアップについて」という内容でお送りしました。
SESも使い方によっては個人のライフスタイルにマッチしたり、技術の探求も行えるものだと思っております。
SESはブラックという言葉だけで選定候補から外すのではなく、自身でキャッチアップしてエンジニアとしてのキャリアプランとして有効活用しながら、仕事の本質として「はたらく」を楽しんでいきたいですね。
ではでは。

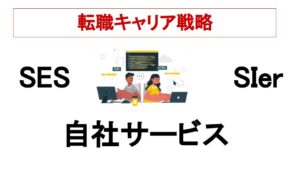
コメント